作品情報
| 制作年 | 2021年 |
| 制作国 | フランス ベルギー |
| 監督 | ジュリア・デュクルノー |
| 出演 | アガト・ルセル ヴァンサン・ランドン |
| 上映時間 | 108分 |
ポッドキャスト配信中
本記事の内容はSpotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcastにてポッドキャストも配信中です。
あらすじ
幼い頃、交通事故により頭蓋骨にチタンプレートが埋め込まれたアレクシア。
引用元:公式サイト
彼女はそれ以来<車>に対し異常な執着心を抱き、危険な衝動に駆られるようになる。自らの犯した罪により行き場を失った彼女はある日、消防士のヴァンサンと出会う。10年前に息子が行方不明となり、今は孤独に生きる彼に引き取られ、ふたりは奇妙な共同生活を始める。だが、彼女は自らの体にある重大な秘密を抱えていた──
ジュリア・デュクルノー監督最新作です。
「カレーの味がした」という名セリフでおなじみ、『RAW~少女のめざめ~』(2016)で衝撃的な長編監督デビューを果たし、いきなりカンヌ国際映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞。
そして二作目の本作『TITANE/チタン』で、もうカンヌ国際映画祭パルムドールを獲得してしまいました。
「どんだけ天才やねん」と思わず言いたくなってしまうデュクルノー監督が今回繰り出してきた設定は、「『RAW』なんてまだまだ普通だったな」と思えてしまうような “常識はずれ” のものでした。
しかしもちろん本作は単に「ぶっ飛んだ映画だったぜ」では終わりません。
そんな “常識はずれ” の領域から、そんな領域だからこそ描けた「愛」が “常識の枠内” に生きる我々に突き刺さる、という素晴らしい「愛についての映画」でした。
規定不能映画

連想する映画はたくさんあるけど
本作は、この映画の中で示されるメッセージを体現するように「ジャンル」という枠組みでは規定し難い映画になっています。
ただ、本作を無理やりジャンル分けに当てはめるとすると、いわゆる「ボディ・ホラーもの」になります。
人間の肉体に対して「異常」や「変化」「破壊」などが起こることによって恐怖を与える映画ジャンルですが、この映画ジャンルの代表監督が、デュクルノー監督が最も影響を受けた映画作家の一人として公言しているデヴィッド・クローネンバーグです。
本作はデヴィッド・クローネンバーグの影響を非常に強く感じさせます。
自動車との性行為に及ぶ主人公からは『クラッシュ』(1996)や、ついでに言うとこれはリドリー・スコット作品ですが、『悪の法則』(2013)において若干『クラッシュ』を連想させるキャメロン・ディアスなんかも思い出します。
性行為による受精を経ずに異形のものを妊娠する展開からは『ザ・ブルード 怒りのメタファー』(1979)からの影響を感じさせます。
クローネンバーグ以外で言えば、「人体と金属」という組み合わせは同じく「ボディ・ホラーもの」の名作である塚本晋也監督の『鉄男』(1989)を彷彿とさせています。
「ボディ・ホラーもの」内の一ジャンルであり、本作が描くテーマの一つにもなっている「妊娠という恐怖」で言えば、ロマン・ポランスキー監督の『ローズマリーの赤ちゃん』(1968)やデヴィッド・リンチ監督の『イレイザーヘッド』(1976)(これは男性目線ですが)などを連想します。
このように本作から連想される映画自体はたくさんあるのですが、本作が優れているのはそれらとはどれとも話が被っておらず、こうした過去の名作たちをうまく取り入れ、独自の新たな作品へ見事に昇華しているというところです。
これこそ「インスパイア」や「オマージュ」のお手本ではないでしょうか。
(呪〇〇戦は本作の爪の垢を煎じて飲んでください)
また、「ボディ・ホラーもの」というジャンル映画的に始まるものの、最終的には圧倒的な「愛」というテーマに辿り着き、もはや「ホラー」的な恐怖の感情は消え去り、愛に満ちた感動のエンディングに至るという点で、厳密に言えば「ボディ・ホラーもの」というジャンルには収まってはおらず、本作全体のテーマとも合わせて考えれば、ジャンル分け自体無意味で無価値とも言える作品に仕上がっています。
そしてこの「規定不能さ」こそ、この映画が描き出す究極の「愛」へ至る鍵となっているのです。
解釈も様々
本来この映画に限らず全ての映画に言えることではありますが、本作はこの「規定不能さ」ゆえに観客による本作に対する解釈が、他の映画に比べてより開かれているように思います。
上で「ぶっ飛んだ映画を見たぜ」では終わらない、と書きましたが、ぶっちゃけ「ぶっ飛んだ映画を見たぜ」で十分なんですよね。(ギャスパー・ノエ作品あるある)
この映画で繰り広げられる「ぶっ飛んだ設定」「ヤバい映像」を目の当たりにし、自分の「知っている世界」や「常識」の外にある領域を垣間見る。
この経験が「自分の知っている世界」や「常識」に対して不可逆なダメージを与え、この映画を見る前と見た後で「世界の見え方」が少し変化する。
これこそ「映画体験」の本義であり、映画に限らず「アート」全般、もっと言えば「表現」が本来担っている役割です。
ということで、今回は「やべえ映画だった」という感想で終わっても良いのですが、せっかくインターネッツの片隅でブログを書いている身ですので、私自身がこの映画をどう受け取ったかを可能な限り言語化してみたいと思います。
この映画の読み解きとして多そうなのは「神話」や「キリスト教」になぞらえた解釈かと思います。
「TITANE=ギリシャ神話の神々ティターン」「俺が神だから息子はキリストだ」「主人公の処女懐胎」「ラストシーンの宗教的な劇判」など、キリスト教や聖書からのモチーフが多く取り入れられています。
ただ、私自身キリスト教にはあまり詳しくないので、宗教とは少し離れた見方で解説と感想を述べていこうと思います。
社会という「共通前提」からの逸脱と倒錯による逆説的な救済

あらゆる枠組みから離脱していくアレクシア
人間が「社会」というシステムを維持するために用意している「共通前提」「常識」という枠組み、いわば「共同幻想」を、主人公アレクシアは次々に否定、逸脱、そして脱出していきます。
アレクシアは自動車事故により臨死体験し、頭にチタンプレートを埋め込まれ、それからというもの自動車という無機物に対して性的欲望を抱くようになります。
アレクシアのこの設定が、『クラッシュ』で描かれた「カークラッシュという<死>や<破壊>を経験した人間たちが、そのカークラッシュにこそ<生(性)>や<創造>を見出す」という逆説的モチーフを想起させます。
しかし、この映画はそうした設定があくまでスタート地点に過ぎません。
アレクシアは自動車事故によって死にかける経験をし、チタンプレートという「無機物」の存在によって生かされます。
ここで全ての始まりである最初の「共通前提からの離脱」が起こります。
アレクシアは<人間=有機物>という人々の「共通前提」から離れた視座を獲得します。
現在、人々の共通前提は<女(男)は男(女)に欲情する>から<人間は人間に欲情する>へ、同性愛も共通前提として認識されるようになってきました。
しかしアレクシアの場合はそれすらも離れ、「人間による無機物への欲情」へと辿り着きます。
同時に人間が持つ「肉体」への欲情、愛着は失われていき、「肉体」そのものへの嫌悪感へと移っていきます。
その結果、アレクシアは人々が自身の肉体に目を向けて欲情する人間(男女問わず)を嫌悪し、殺人も厭わなくなります。
そして人間とのセックスでは嘔吐してしまうようになり、車という無機物とのセックスによってオーガズムを得られるようになります。
アレクシアが抱くこの「肉体そのものへの嫌悪感」という感覚は、デュクルノー監督による「ヌード」描写に始まり「暴力」や「痛み」の演出によって観客へ共有されます。
アレクシアのヌードが頻繁に登場することにより、観客はアレクシアの裸体を見慣れていき、性的なものでも見てはいけないものでもなく、客観的な視座で人間の「肉体」を見るようになります。
観客による「肉体」の客観的な観察と合わせて、「肉体」に対する暴力描写が行われます。
かんざしで耳を貫かれた人間が白目をむき泡を吹いてゆっくりと死んでいく様子。
体を何度も刺された女性が死後もしばらく痙攣し続ける様子。
人間はなぜ肉体が傷つくと痛がるのか。
それを見ている観客も、自分の体が傷ついているわけではないのになぜ目をそむけたくなるのか。
そして肉体を傷つけていくと人間はあっけなく死ぬということ。
つい今まで生きて動いていた人間が、物体と化していくこの気味の悪さ。
気味が悪いのは「死ぬ」ことではなくむしろ「生きている」ことではないのか。
我々は「肉体」を客観視しながらアレクシアの行動を目にすることで、アレクシアと共に我々も「痛み」や「死」によってむしろ人間の「生」とその「気味悪さ」を意識させられることとなります。
次に、彼女は<女性>という枠組みから<男性>へ、さらに言えば最終的には<ジェンダー>という枠組み自体からも離脱していきます。
映画序盤、アレクシアはその外見や「ダンサー」という “女性的” な職業についていることから、ひとまずは女性として社会を生きてきたであろうことが推測されます。
しかし、彼女のダンスが「キャデラック」という “男性性の象徴” の上に乗っかる形で行われていること、彼女が人を殺す際に使用する凶器が「かんざし」(つまり『血を吸うカメラ』(1960)における「三脚」よろしくそれは「男根」の隠喩)であることなどから想像されるように、彼女の内には強い “男性性” を感じさせます。
物語が展開していくうち、アレクシアは内面だけではなく外見も「男性」へ近づいていきます。
行方不明の青年になりすますため、髪を切り、胸にはサラシを巻き、自らの鼻を折り整形まで行います。
(日本の観客としてはここで市橋達也を思い出さずにはいられなかった…)
そしてここからいよいよアレクシアによる「枠組み」からの離脱は本領発揮します。
アレクシアは行方不明の青年になりすまし、その青年の父親であるヴァンサンに「息子」として迎え入れられます。
彼女は<父の娘>から<他人の息子>へと変貌します。
ここでついに彼女は、<男女>に加えて<血縁による家族>という枠組みからも離脱します。
ここまで順調に(?)人々が「社会」を維持するために “当たり前” だと認識している様々な枠組み、「共通前提」を次々に脱出していくアレクシアの身に危機が訪れます。
それが「妊娠」です。
<人間=有機物>、<身体的女性=女性>、<家族=血縁>といった枠組みを否定してきた彼女自身の身に「妊娠」という圧倒的な「身体性」「女性性」「血縁」が立ちはだかるのです。
「社会」という枠組みの内側に生きる我々からすれば、「妊娠」とは(全てではありませんが)大抵の場合「良きこと」として受け入れられます。
しかし、上記のような枠組みから離れもはや「社会」の外部に存在するアレクシアからすれば、自身の体内に新たな「生命」が宿るという「妊娠」は直ちに「恐怖」や「脅威」の対象となるわけです。
そのため劇中でアレクシアは自ら堕胎を図ります。
ところが堕胎は失敗し、アレクシアの体は「女性」として徐々に変化していくわけですが、同時に彼女の肉体がチタンという「無機物」と同化していきます。
アレクシアは、外見や立ち振る舞い的には「男性」を装いますが、妊娠しているという点では「女性」であり、しかし一方で無機物と同化していくという点で「男性」にも「女性」にも属さない。
かと言って彼女が一人の人間であることは間違いない。
つまり、物語が進むにつれアレクシアという存在は、我々が「社会」の中で用いているどの「共通前提」にも当てはめられない、規定不能の存在へと変容していきます。
この映画では、「社会」の中からでは規定できない、「社会」の内側から見れば「非人間的」である存在へと変容していくアレクシアが、彼女が「規定不能」で「非人間的」な存在になっていくがゆえに、ヴァンサンという究極の「人間的な」人物に出会え、彼との間に本当の「人間的であること=愛」を見つけることで救済されるのです。
「人間的」であるがゆえに「異常」に見えるヴァンサン

数々の社会的枠組みを離脱し、人間の肉体を嫌悪し、人間の死も気にかけない、「死」を志向するアレクシアに対し、息子という最愛の存在の不在(おそらく死)を受け入れることができず、自身にステロイドを打ち続けてでも自身の「肉体」に執着する、「生」を志向する存在として登場するのがヴァンサンという人物です。
息子の不在をいつまでも受け入れられない彼は、彼の息子アドリアンであると偽って現れたアレクシアを見て、“本当の” 息子ではないと分かっていながら、自分の息子として迎え入れます。
本作はこの設定が本当によく活きています。
フランスの社会学者ジャン・ボードリヤールによれば、「”人間” であることと”人間的” であることは全く別であり、人間的であることは一種の “過剰” である」と言われています。
「ギブアンドテイク」という言葉があるように、「対価」や「交換」という概念を前提とした関係性(=社会)ではなく、対価の存在しない交換という「過剰」(無償の愛、もしくは不条理な死など)こそが「人間的なるもの」(=世界)であるということです。
ヴァンサンは、アレクシアという他人を息子として無条件で受け入れるという「過剰」によって、アレクシアに人間性を回復させます。
同時に、ヴァンサンもその過剰によって息子を取り戻すことで、肉体的ではない自己を回復します。
「お前が誰であろうと俺の息子だ」
ヴァンサンがアレクシアに放つ本作一番の名セリフです。
このセリフこそが圧倒的な「過剰」ではないでしょうか。
欧米を中心に、今や「親子」という枠組みに血のつながりはさして関係がないことまではだいぶ「共通前提」となってきていますが、この映画はやはりそこでは終わりません。
血のつながりが関係ないどころではなく、息子が女性で妊娠していようが、彼(彼女)が金属と同化し血ではなく油を流すような存在だろうが、そんなことも関係がないとヴァンサンは、そしてこの映画は言ってのけるのです。
ヴァンサンの元妻が言う通り、「社会」という枠組みの中から見れば、明らかに息子ではないアレクシアに対して息子として接しているのは「異常」です。
しかし、この映画はその「異常」な領域にこそ本当の「愛」があると主張します。
“正常” で “リアル” な「社会」という共通前提=共同幻想の中で、アレクシアが息子だとする幻想を見ることで、ヴァンサンはアレクシアと本当の「愛」を見つける「人間的な」存在を体現するのです。
倒錯と逸脱が行きつく先でこそ本当の「愛」にたどり着く

「死」を志向して、人間が作った「社会」という枠組みに対して倒錯と逸脱を重ねるアレクシア。
「生」を志向するがゆえに、死を志向するアレクシアの全てを受け入れるヴァンサン。
ラストシーンで、お互いがお互いの間に本当の「愛」を見出すことにより両者は救済され、この映画もエンディングを迎えます。
ラストシーンでは、アレクシアはヴァンサンのもとに全裸でやってきます。
この映画を通してついに彼女は、かつてのアレクシアでもあるがアドリアンでもあり、ヴァンサンとは他人でもあるが親子でもあり、女性でもあるが女性ではない、男性でもあるが男性ではない、人間でもあるが人間ではない、つまり規定不可能な存在「アレクシア」として現れます。
一方ヴァンサンも身に着けているのはパンツのみ。
そして彼も、ついにアレクシアをアドリアンという息子としての存在ではなく、「アレクシア」という一つの存在として真っ正面から捉え、対峙します。
<親子><他人><男女>など、二人の間にあった規定可能な関係性が全て取り払われた結果、裸の両者が対峙した結果、二人の間に芽生えた「愛」が顕在化します。
妊娠からの「出産」という、人間が持ちうる身体性の極致。
アレクシアは、ヴァンサンの中に「人間性」や「愛」を見出し、その結果この世界に新たな命、彼女がこの世界に存在した証を残して死にます。
この世界で本当の「愛」を知った彼女は最後に死ぬことで、「アレクシア」という存在を縛り付けていた最後の枠組みであった「肉体」からも離脱し、真に救済されます。
一方ヴァンサンは、息子だと認識し続けていたアレクシアを「アレクシア」として自らの意志で再認識することにより、ついに息子という囚われていた過去と決別を果たし、「アレクシア」の生んだ新たな生命と共に未来を生きることを決心し、救済されます。
そしてその「究極の愛」のもと誕生した新たな生命、『ザ・ブルード 怒りのメタファー』ならぬ愛のメタファーは、「肉体」という有機物と「チタン」という無機物が融合した、現在の人間が用意した枠組みでは規定できない存在でした。
社会という枠組みの内側から見れば、アレクシアもヴァンサンも、そしてこの映画自体も「異常」な世界だと思えてしまいます。
しかし、そんな「異常」な世界の中にこそ「愛」や「人間的なるもの」があったのです。
つまり、この映画の世界が「異常」だと感じるのは、視座を「社会」という枠組みの中に置いているからであって、本当に「異常」なのはむしろ我々のいるこの「社会」という枠組み、様々な枠組みを用いれば全てが規定可能であると思い込んでいるこの「現実」ではないのか。
この映画のように、こうしたフィクショナルな「虚構」によってかえって現実世界の「虚構性」が浮き彫りになるという逆説。
映画内で行われるセンセーショナルな演出はただの見世物的な演出では終わらず、我々の世界に対する視座を社会の外へ連れ出すための手段として有効に機能します。
我々にこのような体験を与えてくれる映画こそ、本当にスリリングで面白い映画なのではないでしょうか。
おわりに
「社会からの逸脱」や「自己の破壊」などによる「自己救済」というテーマ自体は、洋邦問わず全くの新しいテーマというわけではありません。
ただ、そのテーマにここまで「ジェンダー」やそのジェンダーにすらとらわれない、無理やり規定するなら「クィア」な要素を入れ込んで、それでいてそれらの要素は全く押しつけがましくないという点で、極めて現代的な最新映画だったのではないかと思います。
ここに一つ付け加えるとすれば、本当にアレクシアが体現したテーマに即すのであれば、もはや「クィア」という言葉で規定することも望ましくありません。
「クィア」という言葉自体、「LGBTQ+」というような言葉によるラベリングから離脱するための言葉でした。
しかし「クィア」という言葉で何かを規定すればそれも一つのラベリングとなってしまい、またそこから逃れようとしても、言葉を使用する限り無限に退行していきます。
そうした無限退行から脱して見せるのがアレクシアであり本作です。
この映画を「ボディ・ホラーもの」や「クィアな映画」という言葉による規定を図るのではなく、『TITANE』として受け入れられるかどうか。
ここに、我々がこの世界で本当の「愛」を見つけられるか否かがかかっているのではないでしょうか。
おわり




















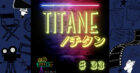

コメント