作品情報
| 制作年 | 2022年 |
| 制作国 | 日本 |
| 監督 | 樋口真嗣 |
| 出演 | 斎藤工 長澤まさみ 西島秀俊 早見あかり 有岡大貴 |
| 上映時間 | 113分 |
ポッドキャスト配信中
本記事の内容はSpotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcastにてポッドキャストも配信中です。
あらすじ
次々と巨大不明生物【禍威獣(カイジュウ)】があらわれ、その存在が日常となった日本。
引用元:公式サイト
通常兵器は役に立たず、限界を迎える日本政府は、禍威獣対策のスペシャリストを集結し、【禍威獣特設対策室専従班】通称【禍特対(カトクタイ)】を設立。
班長・田村君男(西島秀俊)
作戦立案担当官・神永新二(斎藤工)
非粒子物理学者・滝明久(有岡大貴)
汎用生物学者・船縁由美(早見あかり)
が選ばれ、任務に当たっていた。
禍威獣の危機がせまる中、大気圏外から突如あらわれた銀色の巨人。
禍特対には、巨人対策のために
分析官・浅見弘子(長澤まさみ)
が新たに配属され、神永とバディを組むことに。
浅見による報告書に書かれていたのは・・・【ウルトラマン(仮称)、正体不明】。
庵野秀明が企画・脚本を、樋口真嗣が監督を務めた、『ゴジラ』(1954)のリブート『シン・ゴジラ』(2016)に続き、テレビシリーズ『ウルトラマン』(1966)のリブート作品です。
『シン・ゴジラ』(2016)、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』(2020)、『シン・ウルトラマン』(2022)、そして来年公開予定の『シン・仮面ライダー』(2023)の四作を合わせて「シン・ジャパン・ヒーローズ・ユニバース(SJHU)」と呼ばれるメディア・フランチャイズが誕生しました。
ただ、今のところこれは「マーベル・シネマティック・ユニバース」のように各映画の物語が同じ世界観を共有してクロスオーバーするユニバース化ではなく、これらの作品を通して各コンテンツの版権元が合同でイベントや商品開発をするというフランチャイズのようです。
少しがっかりな気もしますが、ハリウッド映画の最前線の真似をしたところで勝ち目はないので、まあそのくらいの感じになるのはやむを得ないのでしょう。
さて、「ゴジラ」に続き日本のサブカルチャーが誇る一大コンテンツ「ウルトラマン」のリブートはどんな作品に仕上がったのでしょうか。
はじめに

当ブログにて邦画を扱うのは今回が初になります。
このことからお察しの通り、私は本作どころかそもそも日本映画に関して完全に門外漢です。
まず、「ウルトラマン文脈」がわかりません。
私の世代的には『ウルトラマンティガ』や『ウルトラマンダイナ』を見ていた世代になるのですが、私自身ウルトラマンシリーズは当時に数回見た程度で、ほとんど何の記憶もありません。
かと言って代わりに「仮面ライダー」や「戦隊ヒーロー」を見ていたかというとそうでもなく、何を見ていたかといえば延々と『トムとジェリー』とか見ている子供でした。
なので基本的にウルトラマンへの思い入れは「ゼロ」です。
そして、「庵野秀明文脈」もわかりません。
『新世紀エヴァンゲリオン』シリーズは後追いでテレビシリーズの第1話から全て鑑賞し、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』(2020)は劇場で鑑賞しました。
このシリーズは大変好みでしたが、『エヴァンゲリオン』シリーズ以外の庵野秀明作品は見たことがなく、彼の作家性や「庵野秀明作品」を語ることはできません。
なので基本的に庵野秀明への思い入れも「ほぼゼロ」です。
さらに、「樋口真嗣文脈」もわかりません。
私が樋口真嗣監督作品で見たことがあるのは『シン・ゴジラ』(2016)のみです。
庵野秀明作品に対してと同じく、樋口真嗣の作家性や作風は全く存じ上げません。
なので基本的に樋口真嗣への思い入れも「ゼロ」です。
最後に、そもそも「邦画」自体に疎いです。
当ブログやポッドキャストの内容をご承知くださっている方々には察しがついているだろうと思いますが、私は邦画鑑賞の経験が極めて乏しいです。
見た映画と言えば、黒澤明とか小津安二郎級の名作か、よっぽど社会現象的に話題になった時です。
(『カメラを止めるな!』とか『鬼滅の刃』とか、一応『呪術廻戦』も見た)
なので邦画自体の歴史的文脈や知識には疎く、基本的に邦画への思い入れも「ほぼゼロ」です。
今回はそんな「ウルトラマンも、庵野秀明も、樋口真嗣も、そして邦画もよく知らない人間」が『シン・ウルトラマン』を見た時、何を感じ、何を思ったのか。
このことについて書き綴った一つの記録になります。
そのため、元ネタの解説や考察といったものは行わないし行えないので、そこはまず初めに断っておきます。
また、本記事を執筆するにあたって何の予習も復習もしていませんので、私が誤解している点も多少あるかもしれませんことも初めに謝っておきます。すみません。
それでは、背景知識ゼロの人間が本作を見て何を感じたのか述べていきたいと思います。
「ウルトラマンらしさ」とは?

先に結論から申し上げておきますと、部分的に楽しんだ箇所はありましたが、作品全体としては楽しめませんでした。
ただ、本作を見ながら「ウルトラマンとは何か」ということについては勉強になったし、興味深くはありました。
しかし、それが好きか、面白いと思ったかというと、あまりそうは思えないのが正直なところです。
ウルトラマンは神ではない
劇中で斎藤工演じる神永新二の体を借りたウルトラマンが「ウルトラマンは神ではない」的なことを言います。
ウルトラマンは、人類を救い人類を統べるために舞い降りた神などではなく、彼が端的に人間へ力を貸したいと思うから、困っている相手を助けたいと思うから、その感情の元行動した結果、人間にはヒーロー的な行動を取ったように見えるということです。
なので本作では、ウルトラマンが一方的に人類を救い人類はただウルトラマンに頼って救われるのを待つだけではなく、ウルトラマンのために人類も「協力」するというクライマックスが用意されていました。
この人類が行う「協力」が取って付けた感満載なのは仕方ないかなという感じですが、ウルトラマンも人間と同じように「リピア」という固有の名前があり、心や感情のある一人の人であるのだという設定。
人類だけが唯一の文明なのではなく、地球人もまたウルトラマンやザラブ、メフィラスなど数多の星人たちの一種に過ぎないという世界観は、古典SFや人類学的な視点で好きな部分ではありました。
不気味、気持ち悪い(のがちょっと面白くなってくる)
神永新二の体を借りれば人間と会話できるものの、ウルトラマンになってしまうと人間と会話できなくなり、人間には黙々と行動しているように見えるということ。
あのぬべっとした立ち姿と猫背のファイティングポーズ。
飛んでいる時はまるで人形を飛ばしているようにしか見えないほど体が硬直していること。
そして極めつけは、その硬直した状態で空中で垂直方向に高速回転し、その回転を使って怪獣に蹴りを入れいるという攻撃方法。
これらの様子を見ていると、ウルトラマンという存在は今でこそ「ヒーロー」として扱われがちですが、本来はやはりどこか不気味で、若干の気持ち悪さも併せ持つ存在なのだということを実感します。
ウルトラマンが高速回転した時は笑ってしまいましたが、この最終的にはちょっと笑える領域に入ってしまう不気味さや気持ち悪さといったものは、多くが元祖『ウルトラマン』で行われた特殊撮影から生じるものを敢えて全力で再現していると容易に想像がつきます。
ウルトラマンファンの多くが本作を好意的に受け取っている様子を見ると、「特撮」というエンターテインメントを非常に上手く再現しているのでしょう。
妙に人間臭い
動きの多くは不気味で気持ち悪いのですが、妙な人間臭さも感じさせます。
それを特に感じるのはやはり戦闘シーンです。
ウルトラマンも怪獣も、とにかく動きがもたもたしています。
中におじさんが入ってる感を隠す気がない、というより本作に関しては全力で出しにいっています。
これもやはりあえてそうしているあたり「ウルトラマンらしさ」の一つなのでしょう。
また、ウルトラマンは内面も最終的には相当人間臭くなります。
人間という存在を好きになってしまったウルトラマンは、きっかけは神永新二という存在だったとしても、なぜそんなにも人間を好きになってしまったのか、ゾ―フィーどころか彼自身もあまりわかってはいないようでした。
しかし彼は「光の国」の掟から罰を受ける、さらには自らの命が危ういという状況になっても、その損得勘定を超えて人間のために尽くそうとします。
この終盤辺りに関しては、はっきり言ってもはやほとんどの人類よりも彼の方が「人間的」でしょう。
その「らしさ」は誰に向けてのものか

これらのようなウルトラマンの「ウルトラマンらしさ」たるものは、本作から様々感じました。
しかし、それが面白いか、楽しいかというと、必ずしもそうだとは言えないと感じました。
本作が、元祖の持っている「特撮ならでは」の要素を全力で再現し、邦画の最新技術によってよみがえらせているのはわかります。
しかし、この時代に全力で「再現」されたこの「特撮ならでは」を面白いと感じられるのは、そもそも一定以上「特撮」というものに理解のある人々だと思います。
端的に言えば、果たしてその「特撮ならでは」が内輪以外にウケるのかは大いに疑問であるということです。
「特撮」という手法を用いて何か新しい表現に挑んでいるのであれば、内輪以外も何か感動できる余地があると思います。
しかし本作は、とにかく完全に「再現」することに全力投球をしているので、それはその再現されている「元」を知っている人々しか感動できないものになっています。
特撮に何の思い入れもない身からすると、本作の「特撮らしい」格闘シーンは、「単に鈍重な」格闘シーンに見えてしまいます。
ウルトラマンが飛ぶときは、それは単に「人形が飛んでいる」ように見えます。
当時こうした表現になっていたのは、当時の技術ではそれが限界だったからです。
そしてそうした表現に観客が感動しロマンを覚えたのは、当時はそんな映像を見たことがなかったからです。
だからスーツアクターが動きにくい着ぐるみを着てもたもた戦っても、それを怪獣バトルとして熱く見られたし、人形を飛ばしているのが明らかでも、ウルトラマンが飛んでいるのだと信じること、言い換えれば「忖度」することができたのです。
当たり前ですが逆に言えば、そうした経験や下地がなければ、単に「着ぐるみだなあ」や「人形が飛んでいるなあ」と思ってしまうということです。
もしくは、「当時はこういう表現をしていたのだな」と歴史の勉強として見るスタンスになります。
つまり、この「特撮らしさ」に今でもロマンを感じ感動できるのは、既にそうした下地のある内輪だけということになります。
もし外野から面白がられているとしたら、それは私が感じた面白さである、「こんな変なものは見たことがない」という興味深さ、そして「へんなの」という方向での面白がり方ではないでしょうか。
「ワクワク」や「カッコいい」といったようなアガり方ではありません。
本作が「特撮ならでは」「ウルトラマンらしさ」を描いたことに感動を覚えるためには、これまでのウルトラマンや特撮の歴史を踏まえている必要があるのだろうと思います。
少なくともウルトラマンや特撮の文脈を知らない私には、ほとんど歴史の勉強として鑑賞するスタンスで、何か感動や興奮を覚えるということはありませんでした。
国家や政治に対する視線のヌルさ

ここも私が本作にノれなかった大きな要因なのですが、国家や政治に対する見方のヌルさが目立ちます。
本作は一応「空想特撮映画」と銘打っているので、「空想だからさ」と言われればそれまでなのですが、政府や周辺の組織に関しては『ジン・ゴジラ』イズムを引き継いで「リアル風」を装っているがために、やはり引っかかります。
まず、ウルトラマンが人間などというどうしようもない存在を好きになってしまうという設定は、彼の感情や思想によるものとしてまだ飲み込めます。
ただ、少しだけ踏み込ませてもらうと、この映画はドラマ性の部分もかなり薄いので、同じく人間ではない存在が人間を好きになってしまう『エターナルズ』(2021)に比べると、相当厳しい飲み込みにくさではあります。
まあそれは置いたとして、どうしても「平和だなあ」と一歩引いてしまうのは、ウルトラマンに協力する人類の描写です。
「天体制圧用最終兵器ゼットン」から地球の破滅を阻止するため、ウルトラマンが提供した知識を使い、有岡大貴演じる滝明久を中心に世界中の科学者が集まって協力するわけですが、地球滅亡の命運が懸かっていようと、世界中が協力することははっきり言って無理です。
丁度最近、「地球滅亡を前に人類は一つになれるのか」を凄まじい切れ味で描いた『ドント・ルック・アップ』(2021)という映画がありました。
これまでの歴史や現在の世界情勢を見れば、地球滅亡の局面における人類の振る舞いというのは、『ドント・ルック・アップ』のようになると考えるのが妥当です。
それをあっさり世界中が協力でき、ぶっつけ本番でばっちり計画成功させてしまうのは、まあやはり「空想」度合いが強すぎるでしょう。
もっと残念だったのは政治に関する描写です。
これも「空想だから」と言われてしまえばそれまでですが、政治批判が批判としてあまり機能していません。
ザラブやメフィラスを前に唯々諾々と自ら率先して言いなりになる日本(だけでなく世界各国だが)が描かれ、他のことに比べて彼らの言いなりになることに関しては仕事が早いなとツッコミを入れることで、多少は日本の政治批判的な目線が描かれていました。
しかし、本作で描かれる日本は現実の日本よりも遥かにまともなため、劇中の日本に対して批判的な目線を注がれても、少し困るところがあります。
劇中の日本はザラブやメフィラスに対して自ら率先して服従していきますが、ザラブやメフィラス級の存在に対してであれば正直仕方ないでしょう。
一方現実の日本は、アメリカに対して全く同様の率先した服従を行っています。
「日米地位協定」や2008年まであった「年次改革要望書」などが良い例でしょう。
「年次改革要望書」は2008年で終了していますが、それは日本がアメリカの要望を聞かなくてよくなったという意味ではなく、わざわざ書類でやり取りしなくても日本はアメリカの言う通りにするから、面倒な手続きを省略しただけという意味です。
それに比べれば、外星人と不平等な条約を結んだ程度の日本など、まだまだ批判や風刺をするに値しません。
「この映画の日本はひどいけど、実際こんな感じだよね」と感じるのが通常の風刺だとすれば、本作は「これくらいの日本で済んでるなら現実より全然良いじゃんね」と思ってしまうということです。
こうした国家観や政治観の薄さが、ウルトラマンファンではないその他の映画ファンが本作を楽しめるはずだった余地を潰してしまっています。
長澤まさみ問題

さて、この部分に関しては本作を楽しんだ方も多少引っかかりがちな部分ではないでしょうか。
既にこの話題に関して様々な意見が飛び交っていますが、私は今回この件に関しては擁護してみたいと思います。
浅見弘子が入れる気合
長澤まさみ演じる浅見弘子に関する印象的な演出の一つは、彼女が自分に気合を入れるために「お尻のあたりを叩く」、そしてその腰回りをズームで撮っているというものです。
まずはこの描写に関して違和感を覚えておられる方がいるようです。
まず、お尻を叩く行為については、自分が自分に対して行っているものなので、行為自体には何も問題ないでしょう。
問題にされているのは、その時に彼女の腰回りをズームで撮るという撮り方かと思います。
擁護派から言わせていただくと、確かに作品にとってどうしても必要な演出かどうかは微妙ですが、あの行動から浅見弘子の溌剌としたキャラクター性がわかるし、映し方についてもお尻ど真ん中というよりは腰に寄っていたし、カットもものすごく短い一瞬だったので、気は遣われていたと思います。
これすら問題視するなら、それよりクエンティン・タランティーノが自身の映画で何度も「女性の素足」を執拗に撮影することや、『アンチャーテッド』(2022)でトム・ホランドが特に必然性もなく上半身裸になっていることを先に問題視した方が良いです。
この「気合描写」に関してもう一つ、クライマックスで浅見弘子が神永新二のお尻を叩くという描写があり、これを問題視している方もいるようです。
男女が逆ならまだしも、さすがに過剰反応ではないでしょうか。
だいたい浅見弘子がお尻を叩いた相手は、斎藤工でも神永新二でもなく、リピアです。人間ではありません。
地球人の女性にお尻を叩かれたリピアがどう感じたかは、地球人の感覚では測れないのではないでしょうか。
浅見側にしても、自分のお尻を叩いている描写によって既に「お尻を叩く程度は性的な行為ではない」と考えるキャラクターなのはわかっているので、リピアのお尻を叩くことに他意がないことは明らかです。
そしてなにより、この演出は神永と浅見がついに「バディ」として関係性を築けた瞬間であることを表すものです。
「バディ」というお互いを信頼し合っている関係の二人が行うボディタッチ(それも女性から男性)がハラスメントになることはないでしょう。
(なるのであればそれは信頼関係ではない=クライマックスが台無し)
要は過剰反応です。
浅見弘子巨人化
これは浅見弘子に関して最大の衝撃シーンでしょう。
メフィラスの手によって浅見弘子が巨人化し操られるという展開ですが、ここも長澤まさみを性的に消費しようとしているとして一部批判がされています。
ウルトラマンファンではない身からするとこの展開の面白さはあまり理解できませんでしたし、浅見の撮り方に対する意図はよくわからかったのでここは正直あまり擁護しにくいです。
ただなぜこんな展開があるのかといえば、リブート元のウルトラマンシリーズを見返すまでもなく、元になったエピソードがあるからだろうことが容易に想像できます。
また、樋口監督が過去に実写版『進撃の巨人』シリーズを監督していることも多少意識して取り入れられたエピソードなのでしょう。
一応劇中で、この巨人化浅見を性的に見ようとする人々を、メフィラスに「下劣な存在」と言わせていたので、「昔のエピソードを再現したかっただけで他に深い意味はないから許して」と言いたいのかなとは少し思います。
神永新二、浅見弘子の匂いを嗅いでしまう
ここが長澤まさみ周辺の描写で、セクハラではないかと最も問題視されているものでしょう。
しかしここに関しても擁護させていただきます。
まず、お尻の件で触れた(お尻だけに)通り、浅見弘子の体臭を嗅いだのは斎藤工でも神永新二でもなく、リピアです。人間ではありません。
なので、人間が人間の匂いを嗅いでいるのではなく、どちらかというと警察犬が捜査のために人間の匂いを嗅ぐイメージの方が適切でしょう。
ただ批判的意見の中で多いのは、そもそもこんな演出が作劇上必要だったのかということでしょう。
どうしても必要だったのかと言われると、確かに無くても十分成立するはずだとは思います。
ただ一つ言えるのは、「匂い」というものは地球に生きる動物にとって重要な要素であるということです。
動物は匂いで敵と仲間を判別したり、それこそフェロモンで交尾の相手を呼び寄せたりと、「匂い」抜きには動物が生きていくことはできません。
今回、多少無理があることは否定できませんが、(地球を救うために)ウルトラマンが浅見弘子の匂いを嗅ぐことは、ウルトラマンという外星人が地球に生息する動物の生態を学ぶことに繋がります。
地球の動物には各個体特有の匂いがあり、人間が、そして浅見弘子という個体にどのような匂いがあるのかを学びます。
これはウルトラマンがまた一つ人間という生き物への理解を深めたと言えるのではないでしょうか。
実際、ウルトラマンが浅見の匂いを嗅ぐ動作は人間のそれとは異なっており、鼻で空気を吸い込むのではなく、ただ顔を近づけるだけというものでした。
この演出から、「斎藤工が長澤まさみの匂いを嗅いでいる」感をなるべく排そうとする努力も窺えます。
そして、このような確実に批判が寄せられるであろう描写をなぜ取り入れたのかといえば、ウルトラマンに少しでも深く人間という生き物を理解させようと、割と真面目に考えてのものではないでしょうか。
ウルトラマンが本気で人間を知りたいのであれば、本を高速で読み続けるだけで十分なはずはなく、身体的なふれあい、そして最終的には人間の営む「性愛」についても学ばなければならないはずです。
しかし直接的な恋愛や性を取り入れてしまうのは「ウルトラマンらしさ」に反するため、ウルトラマンと人間の身体に関わる演出は「匂いを嗅ぐ」や「お尻を叩く」程度に収めたのだと考えられはしないでしょうか。
そこに対して「匂い」や「お尻」すら表現することを許さないのであれば、それはある意味「人間という動物の否定」に繋がるのではないか。
その過剰な自己否定の先に何があるというのか。
身体性に関わらずして、人間ではない存在が人間という存在を理解できたと言えるのか。
人間という存在を理解せずに、人間を好きになったと言うことに果たしてどれだけの意味があるのか。
以上、無理やりな深読みによる、あえての長澤まさみ問題全力擁護でした。
これが邦画大作の限界なのか
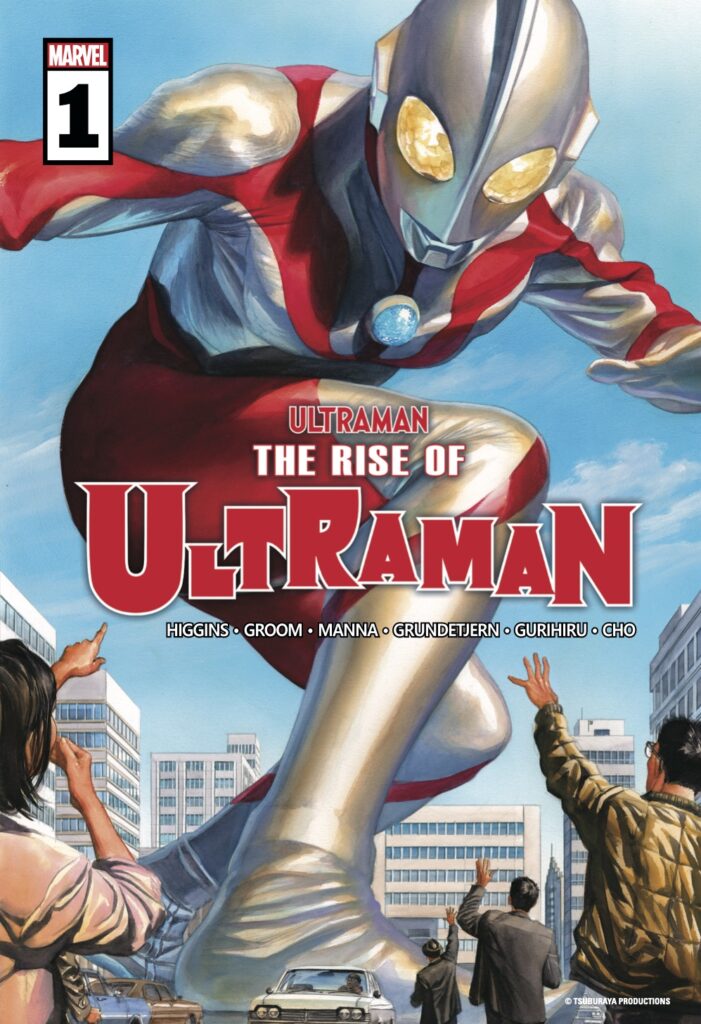
ここまで長々とほとんどが否定的な感想を述べてきました。
最も強く抱いた印象を一言で表せば、やはり「内輪ウケ」です。
ウルトラマン好きによる、ウルトラマン好きのための映画です。
ウルトラマン好きでなければ、いくら過去シリーズの再現やイースターエッグを用意されても響きません。
「特撮ならでは」についても、そもそも特撮好きでなければその「特撮ならでは」に魅力は見出せません。
ということで、この映画から生まれるウルトラマンの新規ファンは正直少ないと思います。
「ウルトラマン」という比較的世界に知られているキャラクターを使って作った大作映画がこんなものなのか。
これが邦画大作の限界なのか。
そう思う面が一切ないとは言えないのですが、一方でこのような方向性こそ邦画大作の歩むべき道なのではないかとも思います。
それはもちろん、日本映画がハリウッドのアメコミ映画と同じことをしても勝ち目はゼロだからです。
まず、日本の人口はこれからも減り続けるため、現在のテレビ局が作る有象無象映画のように国内市場だけにしか目を向けていない作品だけを作っていては、日本の映画業界は衰退の一途を辿るしかありません。
ここでは本作のことを一応大作と言っていますが、大作と言うには予算は少なめなようです。
「ウルトラマン」というコンテンツを使用する映画ですら高予算を用意できないのは、既に衰退が進んでいる証左ではないでしょうか。
日本の映画業界が滅びたくないのであれば、北欧や韓国などのように、世界の観客に向けて作品を作っていく必要があります。
そう考えた時に、当然日本映画は世界的にメジャーなアメリカ映画とは異なるアプローチをとる必要があります。
アメリカ映画の真似事をするのはそもそもできないし、しても勝ち目がないからです。
特にウルトラマンは現在マーベルコミックにも登場しています。
これはつまり、ウルトラマンも将来的にはコミック内でのアベンジャーズとのクロスオーバー、そして最終的にはMCUの一作品として実写映画化もあり得るということです。
そのような計画がアナウンスされているわけではありませんが、理論上は可能なはずです。
そのため、今回『シン・ウルトラマン』がもしアメコミ映画風に作られていたとしたら、そもそもただでさえ勝ち目がないのに、将来MCU版ウルトラマンなんて作られた日には目も当てられません。
だから、『シン・ウルトラマン』はじめ日本映画が世界で戦えるとすれば、まさに本作のような1966年当時の文化や精神をゴリゴリに煮詰めたものを作り、「クールジャパン」などという戯言を世界に売り出す愚昧な行動に走るのではなく、「こんな変なものは見たことがない」という形で世界中の興味を引かせる「へんな日本」という方向性なのではないかと思います。
実際、日本の高度経済成長を世界中に知らしめた『ジャパン・アズ・ナンバーワン』や『バック・トゥ・ザ・フューチャー』(1985)で言及されてきたような日本像というのは20世紀までの話です。
その後の日本像というのは、『ロスト・イン・トランスレーション』(2003)が描いた「変わった国だなあ」というイメージ。
あるいは『キル・ビル』、『ウルヴァリン: SAMURAI』、『ワイルド・スピード X3 TOKYO DRIFT』、『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』、『アベンジャーズ/エンドゲーム』、『ケイト』などなど…で描かれてきた、東アジアの<雑多感>、畳や障子や刀といった近代化以前の<和>のイメージ、ネオンの光る『ブレードランナー』的<レトロフューチャー>など、どれもノスタルジーを含んだイメージです。
そう考えた時に、この『シン・ウルトラマン』は、「日本って変わってるなあ」と「(いい意味での)古さ」を兼ね備えており、しかも常に付きまとう『ブレードランナー』っぽさとは決別できています。
この意味で、結果的に日本映画が世に出した最新の大作映画としては、『シン・ウルトラマン』的なアプローチこそ正しかったと言えるのではないでしょうか。
おわりに
『シン・エヴァンゲリオン』は少々立ち位置が違うとして、『シン・ゴジラ』は『ゴジラ』(1954)を見ていなくてもかなり楽しめる作品だと思いましたが、『ウルトラマン』についてはそうはいかなかったようです。
シン・ジャパン・ヒーローズ・ユニバースは残すところ『シン・仮面ライダー』のみになりますが、今回の『シン・ウルトラマン』を考えると、こちらも仮面ライダーファン向けになりそうですね。
私個人は仮面ライダーに関しても完全な門外漢のため、次回も「内輪」には入れない可能性が高いですが、きっとこちらもアメリカ的なヒーロー映画とはかけ離れた作品になるであろうことが予想できるので、どんな「へんなもの」が見られるのかという意味で期待したいと思います。
おわり
























コメント